 |
 |
 |
 |
 |
 |
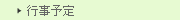 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
日本医療労働組合連合会
〒110-0013
東京都台東区入谷1-9-5
TEL03-3875-5871
FAX03-3875-6270
地図はこちら |
|
|
|
|
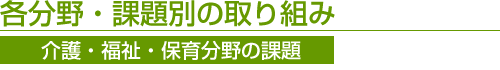 |
 |
| 全労連「米国ヘルパー組織化調査」に参加して |
 |
 |
| ニューヨーク1199支部キムさんと調査団 |
2005年12月11日から22日にかけて、全労連は「米国ヘルパー組織化調査」を実施しました。この調査には、生協労連、自治労連、建設一般、日本医労連、神奈川労連、大阪労連の代表が参加しました。
調査・交流はSEIU(SERVICE EMPLOYESS INTERNATIONAL UNION)のUHW支部(サンフランシスコ)と1199支部(ニューヨーク)のスタッフを中心に行い、日本医労連からは、木口栄・中央執行委員が参加しました。
組織化への努力
サンフランシスコとニューヨークにおける在宅介護労働者の状態は、前者は親族(家族)介護労働者を対象とした組織化であり、後者はエージェンシーに雇用される介護労働者の組織化と、労働者の置かれている雇用形態に違いがあるものの、いずれにも共通していることは、在宅介護労働者が病院やホスピスに勤務する労働者と違い毎日労働者同士が顔を合わせる職場をもたず、地域に点在していることです。
そのため、労働者をいかに見つけるのかについての様々な努力が行われていることです。特に、待ちのオルグではなく積極的に労働者の中にオルグが足を運ぶことが徹底されていることに感銘を受けました。
在宅介護労働者がどの地域に多くいるのか、介護労働者の利用するバス停(駅)はどこが多いのか、こうしたことに対して徹底したそして綿密な調査が行われていること、介護労働者の研修会場で研修を終えた労働者へのアプローチ、時には会社のゴミ箱をあさって労働者名簿を調べあげる等の努力が行われていました。
保険給付や福利厚生に力
労働者を組織する上で、SEIUとして労働者の賃金や労働条件の改善と合わせて、医療保険の給付や子育て支援、介護労働者のスキルアップに向けた教育プログラムへの参画が非常に有効に働いていました。
その背景には、新自由主義の下医療保険は営利市場のもとにあり、保険を買うことが出来ない人が4500万人にも上っている状況があります。こうした中、労働組合が労働者の代表として使用者と交渉し医療保険を買うための資金の拠出を行わせています。そしてその資金でファンドを経営し、家族も含めた医療保険(歯科、眼科も含む)の適用、大学進学の場合の奨学金、サマーキャンプの実施、市民権獲得のための教育など、労働者の福利厚生を進めています。
実践的な労働者教育プログラム
学習教育については、非常に実践的な教育が行われていました。職場委員のための、基礎教育としては「職場委員の役割」「介護労働の内容」「政治分野の教育」のカリキュラムが用意されており、それぞれ4時間から6時間の講義が行われています。また、職場委員には月1回労働者からの電話相談を受ける教育もあり、その実践を通じて労働者の相談に対する問題解決の能力を身につかせる、また経験のある職場委員と新しい職場委員が一緒に家庭訪問をして労働組合の加入を訴えるなどの実践的な教育も行われているとのことでした。さらに、上級職場委員教育のプログラムでは「スタッフ(専従)がいなくても会議運営ができるための会議運営のプログラム」「行動やキャンペーンの中で新たな活動家を発見するための訓練プログラム」「組合のメッセージを正確に伝えるために人前で話す訓練プログラム」が用意されていました。
このように、一度きりの教育に留めることなく、常に労働者を組織し、組織者として成長させるための教育プログラムが制度化されていることが、SEIUがダイナミックに未組織を組織し、組合運動が活性化している大きな要因であるのではないか、と感じました。
介護保険の“消費者”
労働組合の自主的な活動と合わせ、アメリカ社会の持つ特殊性もSEIU運動の前進に影響を及ぼしているとも感じました。日本においては、介護保険の利用者と呼んでいますが、アメリカでは「消費者」と呼ばれています。それは歴史的には障害者運動の中で確立された呼び方と言われました。アメリカでの「消費者」は、非常に強い権利を獲得しています。障害者や介護を受ける人たちであっても人間としての権利が何よりも重視されています。こうした中で、障害者団体や介護を受ける人たちも含めた「消費者」団体の意識と活動が非常に活発であり、そうした方面から介護分野をはじめとした制度の充実を求める運動が一方にあり、そしてもう一方に働く労働者=労働組合の運動があり、その二つがしっかりと手を結び合って組織と運動を前進させている印象を強くうけました。
(文責:日本医労連中央執行委員・木口栄)
|
|
|
|

