 |
 |
 |
 |
 |
 |
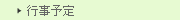 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
日本医療労働組合連合会
〒110-0013
東京都台東区入谷1-9-5
日本医療労働会館3F
TEL03-3875-5871
FAX03-3875-6270
地図はこちら |
|
|
|
|
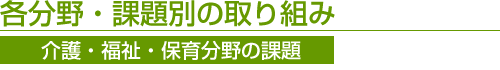 |
 |
| 介護職員処遇改善交付金の概要と問題点 |
 |
岡野 孝信(日本医労連中央執行委員、国民医療研究所研究員)
「一人2万円賃上げ」の掛け声
厚生労働省は2009年8月3日付けで、「平成21年度介護職員処遇改善等臨時特別交付金の運営について」とする厚生労働省老健局長通知(「労発080第1号」)を各都道府県知事に出しまた。
先に、2008年5月、国会で「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が与野党合意で成立しました。これを受けて政府は2009年4月から介護報酬を3%引き上げ、「一人2万円の賃上げを実現する」としました。しかし、介護報酬の引き上げ分はその多くが施設の経営対策として使われ、介護職員の処遇も一定の改善がされたものの、「一人2万円の賃上げ」には、大きく届きませんでした。そればかりか、全く改善のなかった事業所も多くありました。
介護報酬や医療の診療報酬は、一括してそれぞれの事業者に入り、入った報酬をどのように支出するかは、各事業者の自由判断にまかされます。
事業者が得た報酬を、「どのように支出するか、支出の重点を設備投資に置くか、それとも職員の処遇改善に回すかは経営方針に関わることであり、この自由を規制して賃上げに回せと行政は言えない」と強調した若手の厚生官僚がいましたが、当初から「介護報酬3%引き上げ」が労働者の賃上げに回るという保障は介護報酬の仕組みからしてありませんでした。
「2万円賃上げ」のかけ声は、政府の政治的発言でもあり、いわば事業者の「譲歩」による処遇改善に依拠したという側面とともに、賃上げをめぐる労使の「綱引き」に依拠したものでした。その結果は、すでに述べたとおりです。
「平均一人1万5,000円」の交付金
このような中で政府は、今度は介護報酬の引き上げではなく、介護職員の賃金改善を行った事業者に対して、介護職員一人平均1万5,000円の「交付金」を平成24年3月までの2年半の間支給するとして、約4,000億円の補正予算を組みました。介護労働者の劣悪な賃金水準の改善をしなければ、介護職場から若者が去り、政府が多くの批判を押し切って設立した現在の介護保険制度の存続すら危うくなってきたからです。もちろん、今回も、景気や雇用対策、総選挙でのアピールなどとも関連したものでした。とは言うものの、今回の交付金が、実質2年半の時限的なものであっても、介護保険制度の矛盾の現れとして、政府が介護職員への「賃金の現金給付」というところに踏み込んだという点では、特徴的な出来事でした。
ただ、最終の「通知」では、政府自ら公言した一人「1万5,000円」という数値目標は極めて影の薄いものになっています。そこで、明確になってくるのは、厚生労働省が決めた計算式で出された事業者への交付金の支給総額と、事業者から報告される介護職員への支出額、すなわち事業者におけるこの収支の有り様となっています。
「交付金」支給方法の問題点
では、具体的にどのような方法で交付金が支給されるのか。この間、厚生労働省老健局・介護保険課(現在は介護保険計画課)を中心に作業が進められてきました。都道府県では7月中旬より介護事業者への説明会を開き、8月には申請の受付を開始、9月には条令整備・基金造成、交付対象事業所の認定をし、10月より対象サービスの提供を開始、12月には交付金の支払いを行う運びとなっています。
しかし、厚労省の作業は遅れ、最終的な「通知」の都道府県への発送は8月にずれ込み、7月下旬に説明会を開催した東京都などは、「実施要領」(案)のままのバツの悪い説明会となりました。各県での説明会も大幅に遅れ、10月からの交付に対応する「申請期限」を9月末日まで延長する都道府県が多くなっています。
「通知」の作業が遅れた大きな要因の一つは、焦点である各施設への交付金額の算定方法を、その施設の介護報酬と関連させる(「介護サービス毎に定める交付率×介護報酬総額」)ことを基本したことだと思われます。このことによって、さまざま調整しなければならない事がでてきたのでしょう。
今回の交付金の「通知」については、以下のような問題点が指摘されます。
<煩雑な手続き>
第1は、煩雑な手続きです。おおざっぱに言えば、まず、事業者は介護報酬に介護「サービス区分」毎に厚生労働省が推計した「交付率」を掛けて事業所に入ってくる交付金額を見定め、それを基本に賃金の改善計画をつくり、都道府県に申請し、認可されれば交付金が支払われ、交付金が余れば県の基金に返還するというものです。東京都の説明会でも、その煩雑さに参加者からため息が聞こえました。
介護の現場では、正規職員一人1万5,000円、パートなど非正規労働者は労働時間に比例して支給するとすれば、ベターだとは言えないにしても、単純で、きわめて理解しやすい支給方法になるとの声も少なくありません。それは、各事業所の賃金台帳を基本にすれば大筋可能なことです。
<限られた対象者>
第2は、支給対象が限られていることです。「介護職員」ということで、当初、ヘルパーと介護福祉士に限るような話もありましたが、批判も強く、「人員配置基準を満たした上で介護業務に従事している場合」という条件をつけたものの、介護業務に従事していれば、看護師や介護支援専門員・生活相談員でも支給されるというように、ほんの少しだけ「緩和」しました。
しかし、介護分野では多くの職種の賃金水準が低く、ここでの賃金水準を改善するためには、当然のこと、介護分野で働く者全ての処遇改善を、そして全体のレベルアップを考えなくてはなりません。介護分野全体の賃金が極めて低水準にあることを注視することが重要です。
介護の仕事は多くの専門職の協力で成り立っているわけですから、処遇の改善についても、平等に同じ事業所で働く者全体の引き上げを基本にすることが大切です。それは、仕事のチームとしての「仲間意識」や各自の「職能意識」をその職場から育んでいく上からも必要です。
<交付金の趣旨に反する改善額の計算>
第4は、交付金の申請額に関して、処遇改善額の計算方法に関わる問題です。職員の「賃金の改善額」の計算に際して厚生労働省は、今年4月から定期昇給やベースアップ、手当の改善などの賃金改善が実施されている場合、その一カ月の改善分を10月からの改善額の計算に含めても「可」としました。
しかし、そもそも、今回の10月からの改善交付金は、今年4月に介護報酬を引き上げ1人2万円の賃金を引き上げると政府が公言したものの実施できず、新たに補正予算で介護職員一人当たり1万5,000円(平均)を目途に予算化したものです。そして、今回の改善は、あくまでも当面の措置であり、介護職員に求められている抜本的な処遇改善は今後の大きな社会的課題となっています。
このような中で、厚生労働省が今年10月からの改善額の計算に、今年4月からの引き上げ額まで含ませることを「可」とするような見解は、これまでの経過かにして全く矛盾したものです。また、それは、政府の補正予算額の試算を自ら崩すものでもあります。
介護職員(労働者)の対応としては、仮に厚生労働省の計算方法(見解)があったとしても、「交付金」の本来の趣旨に沿って経営側に要求していくことが必要です。例えば、今年4月に5,000円の賃金の改善があった場合、今回は、経営者が2万円(1万5,000円+5,000円)の賃金改善として申請し、職員には10月から1万5,000円を支給するよう要請していくことです。
<労使関係、労使交渉を無視>
第5は、賃金の改善計画策定のための実施「案」では、「交付金」の支給要件に労使の協議を無視するような行政の介入が見受けられました。さすがに、最終の「通知」では若干修正されました。しかし全く消えたわけではありません。事業所にあって、賃金の改善計画をどうするかということは、行政はもちろん、使用者側が一方的に決めるものではありません。当然、労働条件の変更が絡む問題であり、法的にも労使協議が不可欠なものです。
今後の課題
<全ての介護事業所で「交付金」支給を>
全ての介護事業者が「改善計画」を作成し、都道府県への申請をするようみんなで働きかけることです。マスコミなどでの報道も求めたいところです。今回の交付金約4,000億円の補正予算化には、私たちの運動も関わっています。いろいろ問題はあったとしても、全ての介護関係事業者がきちんと交付金を受け取り、これを該当する職員に支給するよう追求していくことも労組の大きな課題です。
<交付金の実現重視を>
「通知」では賃金改善の「方法」について、①基本給(ベースアップ)、②手当、③賞与又は一時金等、と例示していますが、「賃金水準の向上」という目的からしては、当然のこと「基本給の増額」(ベースアップ)が必要です。しかし、労使の合意の困難な場合は、既存の給与体系とは別の、交付金実施期間内の「臨時給与」(例えば毎月1万5,000円)的な位置づけの支給などについても検討し、今回の給付金の実現を重視することが必要です。但し、今回の改善分は、通常の夏・年末の一時金や「定期昇給」と切り離すことが肝要です。
<3年後に向け運動の強化を>
今回の「交付金」の3年後については現在白紙です。これでは、事業者をして労働者のベースアップを基本にした賃金水準の向上に踏み込むことを躊躇させてしまいます。
しかし、日本医労連の要請に対して厚労省は、「3年後に何も無いということは常識で考えられない」、今後、「介護報酬(の引上げ)というものを抜きに考えられない」としました。また、UIゼンセン同盟の要請に対しても、宮島労健局長が「この交付金は安定した職場で生きがいをもって働いてもらうための一つのステップと考えている」と述べています。
私たちは、現時点で3年後のことを固定的にとらえないで、今後の私たちの幅広い運動の強化で3年後の展望を切り開いていくというスタンに立つことが必要です。
<政治的改革と労働運動の前進を>
厚労省は、平成23年度までに介護施設を従来計画よりも4万床、介護職員も10万人増やすとしています。また、総選挙では差はあれ、各党が一斉に介護体制の充実を訴えました。政権が交代し、介護政策にも変化が生じることは必至です。その変化を真に実りあるものにするには、介護労働運動に関わる運動主体の強化が不可欠の課題です。
日本の介護分野は、労働者の結集、組織化が大きく遅れています。既存の労働組合の援助とともに、介護労働者自らが組織化に向けた運動への参加を強めること、また、介護労働者としての権利意識の高揚を図ることが重要です。
国民介護の充実、介護労働者の賃金や人員配置基準の改善、諸権利の確立、そして介護労働者としての働きがいの実現へ向けた運動の強化へ、政治、経済情勢が流動的な今こそ、介護分野の運動主体の確立が急がれていること改めて訴えたいと思います。
(国民医療研究所「月刊国民医療」9月号より)
ダウンロードはこちら → 介護職員処遇改善交付金の概要と問題点
|
|
|
|

